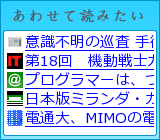麻生首相はことの顛末を知っているので強面なのに公務員制度改革に踏み切れない。という間に世界経済危機がやってきて政治課題が苦手な経済問題になってしまった。与謝野大臣を引っ張り出し丸投げしたが経済問題が片付くまでは得意の外交はアジェンダにならない。
全く出る幕なしの麻生首相に対して民主党は政権交代と息巻く。自民党支持率が低下したと喜ぶが、民主党も仲良く支持率を落とした。民主党優勢に変わりはないが、あくまでも自民党に比較して。自民党を支持しなくなった人が民主党を支持するわけではない。逆に自民党がサプライズを仕掛けて支持を取り戻せばあっという間に反転する。
民主党の今のマニュフェストは農業戸別補償や年金対策などかつての自民党のばらまきと見紛うばかり。加えて、自治労や公務員組合、日教組などに支持されていて、公務員改革など出来そうな感じがしない。党幹部に日教組の重鎮がいるなど官から民へに逆行しそうだ。
自民党と民主党が共に支持率を下げた背景にはどちらにも失望している国民の姿が映る。正直に言えば次回の選挙では投票に困りそうだ。直感も理性も働かない。
いや〜参った参った…