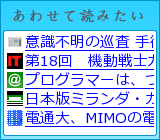2011年6月9日木曜日
憲法改正論議を!
2011年6月8日水曜日
忠誠と盲信の違い
2011年6月3日金曜日
菅首相の退陣時期に対するドタバタについての所感
野党の提出した不信任案に賛成しようとした人たちは「菅首相ではこの難局を乗りきれない」と口々に言っていた。なのに菅首相が「メドをつけて退陣する」と言ったら矛を収めるとは頭が悪い。「難局を乗りきれない」とは「メドをつけられない」ということだ。だから延々と続投することになる。不信任賛成派は菅首相が辞任会見をするまで手綱を緩めるべきではなかったが、善良な鳩山前首相に従ってしまった。
結果的に菅首相に続投のお墨付きを与えてしまった反対派は大量離党でもする以外にやることがなくなった。
2011年6月2日木曜日
こんな時期に不信任なんて非常識な!という意見に対する反論
不信任を否定する意見の骨子は
1)一時たりとも遅延させることの出来ない被災者支援の遅れにつながる
2)一時たりとも遅延させることの出来ない福島原発対応に穴が空く
しかし、今までの菅内閣の実績を見てみると、1)被災者支援はNPOに丸投げで補正予算は遅々として進まず、2)福島原発は初動を含めて対応がお粗末で、東電救済ばかりが目立つ。菅内閣が"遅い"だけなら未だしも優先順位が自分勝手で、国民の為になってない。
だから、一時的な停滞があったとしても、能力がないものを替えるというのは正しい。無能なものを替えないのは組織としては不誠実だろう。
2011年5月27日金曜日
QCD(F/S)->E/I
これは1)人材は有限であり、2)時間は有限であり、3)資源は有限であるという物理的な制約によるものだ。しかし、最近これら三つの要素に加えてもう一つ加えなければいけないのではないかと思う様になった。それは機能/サービスレベルである。機能やサービスレベルを品質に含めて考える場合が多いがそれでは混乱する。最高の鉛筆は機能はたった一つしかないが品質は上等である。
UNIQLOはスタンダードなカジュアル衣料に絞らながら、高品質を実現している。マクドナルドは規格化したオペレーションで安価で品質の良い食事を提供する。逆に、ディズニーリゾートは品質と機能を高めるためにコストは高い。しかし、その品質と機能が客の心を掴み高い価格でもリピーターを生むのだ。
Appleはどうか?iPod、iPhone、iPadは品質は良いが高い。購入までに待たされることもある。機能はと言えば、そんなに高機能ではない。機能はユーザー自身がインストールしたり、時には開発したりする。
ユーザー自身が開発するという点でこれらのiシリーズは正しくパーソナルコンピュータの後裔である。なら、こんな未完成なものにこれほど多くの人が魅了されるのだろうか。そこには体験:Experience や感動:Impression といったものがある。物理的な制約に閉じ込められたQCDF/Sと違い、これらには限界がない。問題があるとすればそのような製品やサービスを開発するにあたって、大抵の場合は"上司"という人には理解されないものだ。
だから、感動的な製品やサービスを生み出すのは多くの場合は上司を持たない起業家になるのだろう。
2011年5月26日木曜日
連続性で見るべきものを非連続に見、非連続で考えるものを連続的に考えるヒト
連続的に考えるものに日々の事業管理がある。前年や前月、前週や前日の結果を評価して何らかの打ち手を考え実行し、その結果を検証して次の手を考えて実行する。この所謂"PDCA"サイクルを回して改善を積み重ねるのは現場責任者だ。粘り強く端々に目配りする実直なタイプが合っている。
非連続な思考を要するのは事業環境の変化によって、改善では追いつかないほど悪化した事業の再生や改革などである。これは今の事業が置かれた環境の徹底したリサーチと深い洞察、あらゆる可能性を排除しない自由な発想が化学変化を起こして発現する。論理的な思考と論理を逸脱する発想を合わせ持ったバイタリティ豊かな人が必要だ。改革は一人では出来ないので周りを巻き込み没頭させるカリスマも必要だったりする。
ところが、連続的な改善を任された責任者が突拍子もないアイデアを振り回してみたり、非連続な改革も求められる人が改善テーマしか持ち出せなかったりする。例えば、コスト改善による収支改善を求められる製造部長が新しいサービスや商品開発に手を出すなどということだ。或いは、抜本的なコスト構造の改革を望まれているのに桁が一つ小さい改善テーマを持って来ることがある。これは一つにはその人の能力が足りないというのが理由だ。
連続的な改善を非連続なアイデアで乗りきろうとする人には基本的なオペレーション分析のスキルが不足しているケースが多い。なので何が問題なのかをデータで把握出来ない。そのために改善すべきポイントが分からず、改善点がないので思い切った手を打とうとする。重要なのは非連続な発想にもデータは必要なので、天才でもない限り、大抵は役に立たないということだ。
非連続に連続的な改善を持ち出す人も基本的なスキルが足りない。データに強い場合が多いので問題を把握しているのだが、アイデアの出し方が分からないので思い切った提案は難しい。しかし、どちらもその責任を負わせた側にも問題がある。能力が足りないものを何の教育も無しに責任を負わせるのは経営者の見識が足りない。
更に、非連続な発想を経営者としての信頼を背景として引き出せないのは経営者の責任だろう。大抵の場合、そういう立場の経営者も追い詰められていて、取り組む課題が混乱していることが多い。何を優先して、限られたリソースを何に注ぎ込むか?
そう。自分が投入出来るリソースが限られていることに気付いてないケースも多い。自分自身の時間も含めて、不調な事業にあっては投入出来るリソースが僅少のことが多い。なのに不要不急のことにかまけていることが多い。
事業にあたって、「連続的な」テーマと「非連続な」テーマがどちらかだけということは少ない。基本的に、連続的な改善で補えないギャップを戦略的に埋めるのが求められる姿だろう。しかし、見栄えの良い非連続な戦略的打ち手に真っ先に飛び付くヒトが多い。今の場面で求められているモードを見極めないといけない。
2011年5月13日金曜日
東北の復興が利権にならない政治家のリーダーシップを望む
有明干拓事業でも感じたが、何故耕作不適地にわざわざ農地を拓こうとするのだろうか。あの干拓事業で農地が出来る長崎は入り江と山勝ちな地形で農業には不向きである。干拓事業が持ち上がったのは長崎の人口が今以上に増えて食料が不足するから干拓事業開始当初は増加する人口増に備えて農地を拡大して農業生産を増やすのは意味があっただろう。しかし、実際には人口は減少して農地拡大は不要になり、耕作放棄地の増加でも食料が不足することは全くおきてない。最初の条件が変わっても当初計画を変えられないのは官僚主義の悪弊である。
こういう無駄や矛盾を解消して全体最適を図るのが政治家の役割であろうと思う。